野菜生活スムージーは体に悪い?初心者の疑問を解決

野菜生活スムージーは体に悪い?初心者の疑問を解決
こんにちは。スムージライフの運営者です。
手軽に野菜を摂れると思って飲んでいる野菜生活スムージー。「体に悪い」なんていうキーワードを見ると、え、本当に?と不安になってしまいますよね。私もその一人でした。
実際に、市販のスムージーの砂糖不使用の表示の意味や、含まれている糖分のこと、食物繊維がどうなっているのか、ジュースとの違いは?など、気になることがたくさん出てきました。
また、香料などの添加物は大丈夫なのか、メーカーが推奨する飲み方や、おすすめの飲むタイミングはいつなのか、市販品を選ぶときのポイント、そしてやっぱり自家製スムージーと比較したほうが良いのか…。(気になることが多すぎです!)
この記事では、そんな「野菜生活スムージーは体に悪い?」という疑問について、スムージー初心者の私が徹底的に調べた内容を、分かりやすくシェアしていきたいと思います。同じように不安に思っている方の、なにかしらの参考になれば嬉しいです。
- 砂糖不使用と糖分の関係がわかる
- 市販品と自家製スムージーの違いがわかる
- メーカーが推奨する飲み方やタイミングがわかる
- 市販品を選ぶときのポイントがわかる
「野菜生活スムージーは体に悪い」の真相は?

手軽に野菜が摂れると人気の野菜生活スムージー。でも、「体に悪い」というウワサもあって、どっちなの?と迷ってしまいますよね。私も健康のためにと思って飲んでいた一人なので、このキーワードはかなり気になりました。
調べていくと、どうやら毒だ!とか危険だ!という単純な話ではなく、その中身や製法を「知らずに飲む」ことに、いくつかの注意点があるみたいです。
ここでは、まず多くの人が気になっている糖分や食物繊維、そして製法について、私が調べたことをシェアしますね。
砂糖不使用と糖分の関係
まず、私が一番「え?」と思ったのが、この「砂糖不使用」という言葉の裏側です。
多くの野菜生活製品のパッケージには、砂糖不使用と書かれていますよね。これを見ると、なんとなく甘くないのかな?糖分控えめなのかな?って思いませんか?
でも、これは「製造工程で、お砂糖(いわゆるショ糖やテーブルシュガー)を添加していませんよ」という意味で、決して糖分ゼロや糖類オフという意味ではないんです。
じゃあ、あのしっかりとした甘みや、栄養成分表示に書かれている「糖類」はどこから来ているのか?
それは、主に野菜や果物の果汁、特に「濃縮還元果汁」に由来する糖分なんですね。
濃縮還元というのは、一度水分を飛ばして、輸送コストなどを下げるためですが、後から水分を加えて元の濃度に戻す方法です。この工程自体で糖の総量が増えるわけではありませんが、原料配合や濃度設計によっては、味として甘みがはっきり感じられることがあります。
栄養成分表示の「糖類」をチェック!
ここで大事なのが、商品の裏にある栄養成分表示のチェックです。見慣れないと難しいですが、ポイントは「炭水化物」の項目です。
例えば、野菜生活100 オリジナルの200mlパックだと、公式サイトの情報では糖類が13.1g含まれています(出典:カゴメ株式会社 商品情報)。
栄養成分表示の読み方(例)
炭水化物 15.0g
- 糖質 14.0g
- 糖類 13.1g
- 食物繊維 1.0g
(※数値は「野菜生活100 オリジナル 200ml」の一例です)
こんな風に、「炭水化物」は「糖質」と「食物繊維」に分けられます。そして「糖質」の一部が、甘みの元になる「糖類」、つまりブドウ糖や果糖などのことです。
スティックシュガー(1本3g程度)に換算すると、約4本分…(※スティックシュガーは1本約3gとしての目安換算)と考えると、結構しっかり入っているのが分かりますよね。
「砂糖を加えてないのに、こんなに糖類が入ってるの!?」というのが、私の正直な驚きでした。
これが「体に悪い」と検索される、一つ目の大きな理由なのかな、と思います。次のセクションで、この「糖類」について、さらに深掘りしていきますね。
気になる糖分の種類とは?
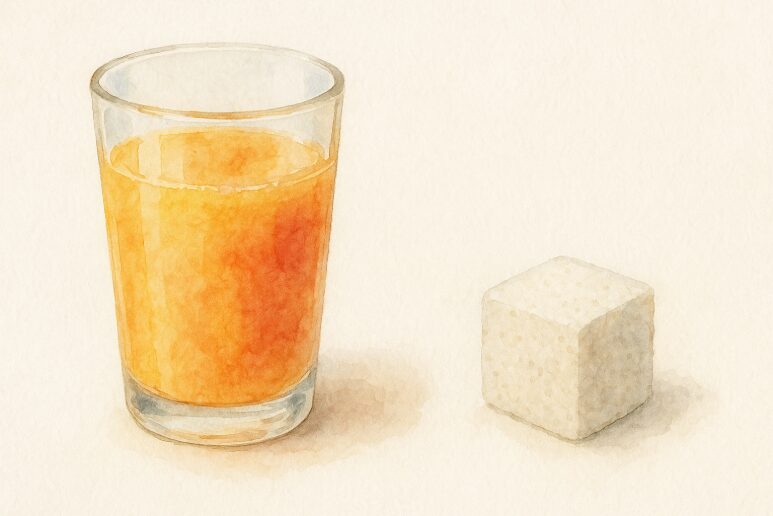
砂糖不使用だけど、野菜や果物由来の糖類はしっかり入っている、ということが分かりました。
ここで次の疑問です。「でも、それって果物由来の"天然の"糖分だから、お菓子やジュースの砂糖とは違ってヘルシーなんじゃないの?」
私もそう思っていました。でも、ここで「遊離糖類」(フリーシュガー)という、ちょっと専門的な言葉が出てくるんです。
これは、WHO(世界保健機関)が「この糖分は、摂りすぎに注意してね」と呼びかけている糖類のカテゴリーのことです。
WHOが注意を呼びかける「遊離糖類」とは
遊離糖類って、初めて聞く方も多いかもしれません。私も今回調べて初めて知りました。
WHOの定義をすごく簡単にまとめると、こんな感じです。
「遊離糖類」に含まれるもの
- メーカーや私たちが添加する糖類(砂糖、ブドウ糖、果糖など)
- シロップ、蜂蜜、メープルシロップなど
- そして、ここが重要! → 「フルーツジュース」「フルーツジュース濃縮還元」「野菜ジュース」に"天然に"含まれる糖分
そうなんです。たとえ果物や野菜に「天然に由来する」糖分であっても、それがジュースや濃縮果汁の形になった時点で、「遊離糖類」として扱われるんです。
なぜかというと、生の果物を丸ごと食べるときは、食物繊維と一緒になっているので糖分の吸収が比較的ゆっくりになります。でも、ジュースのような液体の形にすると、その食物繊維(特に不溶性)が取り除かれてしまうため、糖分が体に一気に吸収されやすくなる、と考えられているからだそうです。
WHOは、この遊離糖類の摂取量を、1日の総エネルギー摂取量の10%未満を推奨上限とし、できれば5%未満を理想に抑えることを強く推奨しています。
(出典:WHO Guideline: Sugars intake for adults and children)
1日の理想量(5%)ってどれくらい?
1日の総エネルギーを2000kcalと仮定した場合、その5%は100kcal。糖類は1gあたり約4kcalなので、1日あたり約25g未満が「理想」の目安になります。
ここで、市販の野菜ジュースの糖類量を見てみると…
| 製品例 (200mlあたり) | 糖類量 (1本あたり) | WHO理想基準(25g)に対する充足率 |
|---|---|---|
| カゴメ 野菜生活100 オリジナル | 13.1 g | 52.4% |
| 伊藤園 1日分の野菜 | 11.7 g | 46.8% |
| キリン 48種の濃い野菜 | 18.0 g | 72.0% |
※各社公式の最新栄養成分表示に基づく(取得日:2025年11月)。充足率はあくまで目安です。
※糖類量は配合やリニューアルで変わることがあるため、最新の公式表示(またはラベル)を確認してください。本文内の数値は取得時点の参考値です。
出典:カゴメ | 伊藤園 | キリン
この比較が示すように、健康的なイメージのある野菜生活100 オリジナル1本(200ml)を飲むだけで、WHOが「さらなる健康上の利益をもたらす」として推奨する理想的な1日の遊離糖類摂取目安量(25g)の、なんと半分以上を消費してしまう可能性があるんです。
これを食事としてではなく、水やお茶の感覚で1日に何本も飲んだり、食事+ジュース、間食+ジュース…と続けていたら、どうなるでしょう?
これが、「体に悪い」や「太る」という懸念の、最も大きな科学的な根拠なのかなと、私は感じました。
液体カロリーの摂りすぎに注意
液体状のカロリー(糖類)は、満腹感を得にくく、つい飲みすぎてしまいがちです。食事と一緒に摂る場合、そのカロリーがそのまま上乗せされる可能性にもなります。
製品自体が悪いというより、その飲み方や飲む量が体重増加などに繋がる可能性は、十分に考えられそうですね。
※健康状態(血糖値など)に不安がある方は、摂取について専門家にご相談ください。
スムージーとジュースの違い
次に気になったのが、「スムージー」という名前です。
皆さんは「スムージー」と聞くと、どんな飲み物を想像しますか?
私は、カフェや自宅のミキサーで、野菜や果物を丸ごと(皮や種は除くこともありますが)、氷やミルクと一緒に攪拌(かくはん)した、ちょっとドロッとした飲み物をイメージしていました。英語で「Smoothie(滑らかな)」という名前の通り、あの食感が特徴ですよね。
自宅でブレンダーやミキサーで作る場合、食材を「丸ごと粉砕」(ブレンディング)するので、食物繊維もビタミンも、基本的に「量としては」そのまま保持されます。(細かくはなりますが)
でも、調べてみると、「野菜生活スムージー」を含む多くの市販の野菜飲料は、その製法が根本的に違うみたいなんです。
市販品の多くはジュース化(搾汁)
市販品の多くは、家庭で作る「ブレンディング」(丸ごと粉砕)ではなく、まず搾汁(さくじゅう)、つまりジュースを絞る、という工程を経ています。
野菜や果物を圧搾してジュースを絞り、そのジュース(液体部分)をベースにしているんですね。
「え、じゃあ普通のジュースじゃん!」って思いますよね。
もちろん、製品によっては、そのジュースに後から野菜のピューレ(すりつぶしたもの)や、別途加工した食物繊維などを加えて、スムージーらしい、とろみや満足感を再現しているものも多いです。
でも、スタート地点が「丸ごと粉砕」ではなく「ジュース」(搾りかすを除く)である、という点は、私たちがイメージする「スムージー」とは大きな違いかなと思います。
これが「体に悪い」と直結するわけではありませんが、「スムージー」(丸ごと)という名前から期待される健康効果(特に食物繊維)と、製品の実態(ジュースベース)との間にギャップがある、ということは知っておくべきポイントだと感じました。
なぜ食物繊維が少ないのか?

前のセクションで、市販のスムージーの多くは「搾汁」(ジュース化)がベースになっている、という話をしました。
この「搾汁」の過程で、栄養的に影響を受けやすいのが食物繊維です。特に不溶性食物繊維です。
食物繊維の不溶性と水溶性
ここで、簡単に食物繊維のおさらいです。食物繊維には、大きく分けて2種類あります。
① 不溶性食物繊維
- 水に溶けにくい繊維。
- 野菜の硬いスジ、皮、穀物の外皮などに多い。
- 腸の蠕動(ぜんどう)運動を活発にして、便通を助けると言われています。
- 私たちが繊維感として感じるのは、主にこれですね。
② 水溶性食物繊維
- 水に溶けてネバネバする繊維。
- 海藻、こんにゃく、果物のペクチンなどに多い。
- 食後の血糖値の上昇を緩やかにしたり、腸内環境を整えたりするのを助けると言われています。
のどごしと食物繊維の関係
市販の野菜ジュースやスムージーの製造工程では、野菜や果物を圧搾してジュースを絞ります。このとき、皮や種、硬い繊維質といった「不溶性食物繊維」の多くが「搾りかす」として残ります。
なぜ、わざわざそんなことをするのか?
それは、のどごしを良くし、飲みやすい食感にするためだそうです。たしかに、繊維のスジが残っていて、口当たりがザラザラしていたら、毎日ゴクゴクとは飲みにくいかもしれません。
この製法のため、搾汁を主体とする製品では、私たちが「丸ごと」のイメージから期待する「不溶性食物繊維」は、相対的に少なくなる傾向があります。
ただし、これはすべての製品に当てはまるわけではありません。「野菜生活スムージー」シリーズの中には、食物繊維を「売り」にして、後から食物繊維(水溶性など)を添加し、1本で多くの食物繊維が摂れるように設計されている製品もあります。例えばグリーンスムージーなどがこれにあたります。
食物繊維が少ないのではなく、「製品のタイプ(搾汁ジュースタイプか、食物繊維添加タイプか)によって、含まれる食物繊維の量や種類が大きく異なる」というのが、より正確な理解かなと思います。
加熱処理で失われるもの
市販のスムージーが「体に悪い」と言われるかもしれない理由の3つ目は、加工の問題です。特に加熱殺菌処理による栄養素の変化です。
スーパーやコンビニで売られている「野菜生活スムージー」は、冷蔵コーナーだけでなく、常温の棚にも並んでいますよね。そして、賞味期限も数ヶ月と長いです。
なぜ、生の野菜や果物を使っているのに、こんなに長持ちするのでしょうか?
それは、製造工程で、腐敗の原因となる菌を殺菌し、長期の常温保存を可能にするため、加熱殺菌または無菌充填といった工程を経ているからです。
この加熱処理は、食品の安全性を保つために非常に重要な工程ですが、残念ながら、熱に弱い栄養素にとってはダメージとなる可能性があります。
熱、光、酸素に弱いビタミンC
加熱処理で失われる(減少する)栄養素の代表格が、ビタミンC(L-アスコルビン酸)です。
ビタミンCは、熱、光、そして酸素に非常に不安定な、デリケートな栄養素です。
食品科学の分野では、UHT(超高温殺菌)や従来のパスチャライゼーションといった加熱殺菌処理がビタミンCの損失を引き起こすことは広く知られています。その減少率は、製品のpH(酸性度)、加熱温度、処理時間、酸素への曝露など多くの要因に左右されるため一概には言えません。
さらに、ビタミンCの劣化は、製造後も続きます。
ビタミンCは保存中にも徐々に低下します。総説レビューによれば、保存温度や期間によって数か月で大きく減少し、常温6か月で2〜8割程度の低下が報告されています(条件により幅があります)。
生の野菜や自家製スムージー(作った直後)のビタミンCを100とすると、市販の長期保存可能なスムージーで、それと同じ量のビタミンCを摂るのは、難しい可能性がある、と言えそうです。
「添加物」としてのビタミンC
この加工損失を補うために、製品によっては栄養強化目的でビタミンCが「添加物」として別途加えられている場合があります。
原材料表示に「ビタミンC」と書かれている場合、それは酸化防止剤として、あるいは栄養強化として加えられたビタミンCである可能性が高いですね。
加熱処理で得られるもの
前のセクションで、加熱処理でビタミンCが減少しやすいというデメリットをお話ししました。
じゃあ、加熱処理は悪でしかないのか?というと、実はそうとも言えないんです。加熱処理には、栄養面での明確なメリットもあります。
それは、特定の栄養素の生体利用率、つまり体への吸収率(バイオアベイラビリティ)が向上する点です。
脂溶性カロテノイドの吸収率がアップ
メーカー(カゴメ)の公式サイトなどでも、このメリットは積極的にアピールされています。
具体的には、リコピンやβ-カロテンといったカロテノイドと呼ばれる色素成分です。
吸収率がアップする栄養素の例
- リコピン:
トマトの赤い色素。抗酸化作用が注目される栄養素ですね。 - β-カロテン:
ニンジンやカボチャの黄色~オレンジ色の色素。体内でビタミンAに変わります。
これらの栄養素は「脂溶性」、つまり油に溶けやすい性質で、野菜の硬い「細胞壁」の中に閉じ込められています。
生の野菜のままだと、この細胞壁が硬くて、私たちが噛んだり消化したりするだけでは十分に壊すことができず、中の栄養素が吸収されないまま排出されてしまうことも多いんだとか。
しかし、ジュースにする際の「加熱処理」によって、この硬い細胞壁が破壊されます。
その結果、中に閉じ込められていたリコピンやβ-カロテンが外に放出され、生の野菜から摂るよりも、ジュースなどの加工品から摂るほうが、体への吸収率が格段に良くなるとされています。
栄養プロファイルのトレードオフ
ここまでの話をまとめると、市販のスムージーを選ぶことは、一種の栄養的なトレードオフなんだと分かります。
市販スムージーのトレードオフ
【失うもの・少ないもの】(デメリット)
- 不溶性食物繊維(搾汁主体の場合、少なくなる傾向)
- ビタミンC(加熱・保存で損失しやすい)
- 生の野菜の「丸ごと」という全体的な栄養
【得るもの】(メリット)
- リコピン、β-カロテンの吸収率向上(加熱で向上)
- 手軽さ、利便性(最大のメリット!)
- 長期保存性
「食物繊維やビタミンC」を重視するなら自家製スムージー(生)が優位ですが、「リコピンやβ-カロテンの吸収」を重視するなら市販品(加熱)にも利点がある、ということです。
どちらが良い・悪いではなく、自分が何を優先したいのかを理解して選ぶのが大事なんだな、と痛感しました。
「野菜生活スムージーが体に悪い」は誤解?

さて、ここまでは主に糖分、食物繊維、ビタミンという栄養面から、市販スムージーが「体に悪い」と懸念される理由を深掘りしてきました。
でも、話はそれだけではありません。「添加物」への不安や、そもそも「血糖値」への影響はどうなのか?といった、さらに複雑な論点もあります。
このセクションでは、そうした懸念に対するメーカー側の研究や、私たちが上手に付き合っていくための飲み方について、さらに調べたことをシェアしていきますね。
気になる添加物(香料など)
「体に悪い」と検索する人の不安の中には、原材料表示に書かれている香料やpH調整剤といった、カタカナの食品添加物に対する漠然とした不安も含まれていると思います。
よく分からない化学物質=体に悪いというイメージ、私にも少しありました。
でも、これらも一つずつ、その役割と安全性について調べてみました。
pH調整剤の役割と安全性
pH調整剤(ピーエイチちょうせいざいと読みますが)は、食品の酸性度(pH)を適切な範囲に保つために使われます。
ジュースは、時間が経つと腐敗したり、色が変わったり(変色)、風味が落ちたりしますよね。pHを調整することで、腐敗や変色を防ぎ、製品の品質と安全性を長期間維持する役割があるんです。
「じゃあ、その中身は何なの?」というと、その実態は主にクエン酸やリンゴ酸、酢酸ナトリウムといった、食品(例えば柑橘類や酢など)にもともと含まれている安全な有機酸であることがほとんどです。
香料の役割と安全性
香料、つまりフレーバーは、製品の風味を一定にするために使われます。
野菜や果物は、収穫時期や産地、その年の天候によって、どうしても風味が微妙に異なります。でも、工業製品として「いつでも同じ味」を提供するためには、香料で最終的な風味を均一化し、商品としての安定性を高める必要があるんですね。
日本で使用できる香料は、厚生労働省が安全性を評価し、使用が許可されたもののみが、ごく微量に使われています。
添加物より心配すべきこと?
もちろん、添加物は絶対に避けたいという考え方もありますし、それは個人の自由な選択だと思います。
ただ、私が調べた限りでは、市販スムージーに含まれるこれらの添加物が「体に悪い」という懸念は、科学的な根拠に乏しいかな、と感じました。
むしろ、私たちが本当に健康影響を考慮すべきなのは、安全性が確認された微量の添加物よりも、ここまで見てきた高濃度の遊離糖類(糖分)や不溶性食物繊維の含有量という、製品の栄養的な本質のほうにあるのではないか、というのが私の個人的な結論です。
メーカーが推奨する飲み方
さて、ここまでの話だと、市販のスムージーは「糖分が多くて食物繊維が少なく、ビタミンCも壊れた飲み物」という、ネガティブな印象ばかりになってしまいますよね。
しかし、メーカー側もこの糖分(血糖値)の問題については、しっかり研究をしているようです。
そして、その研究結果として「体に悪いどころか、むしろ食後の血糖値上昇を抑える効果が期待できる」という、私たちの懸念とは真っ向から対立するようなデータを公表しているんです。
それが、カゴメが提唱する「ベジタブルジュース・ファースト」という概念です。
食前30分が鍵だった
ここで非常に重要な注意点があります。これは「野菜生活スムージー」単体の研究ではなく、一般的な「野菜ジュース」を用いて行われたヒト試験研究(健常な成人を対象にしたもの)に基づいています。
研究方法を簡単に言うと、「白米(糖質)だけを食べた場合」と、「白米の前に『水』『野菜サラダ』『野菜ジュース』のどれかを摂取した場合」とで、食後の血糖値がどう変わるか比較したものです。
その結果、驚くべきことが分かりました。
「ベジタブルジュース・ファースト」研究の結果
- 食事の「30分前」に野菜ジュース(または野菜サラダ)を摂取すると、食後の血糖値の急上昇が、水だけを飲んだ場合と比較して有意に抑制された。
- この抑制効果は、食事の「10分前」よりも「30分前」のほうが、より顕著だった。
- 一方で、食事と「同時に摂取」した場合では、この抑制効果は見られなかった。
つまり、「食事30分前の野菜ジュース摂取」は、「ベジタブル・ファースト」(食事の最初に野菜を食べる)と同等の血糖値上昇抑制効果が期待できる、という結果でした。
なぜ血糖値上昇が抑えられるのか?
ジュース自体にも糖分が含まれているのに、なぜ食後の血糖値が抑えられるのか?不思議ですよね。
そのメカニズムは、ジュースに含まれる「水溶性食物繊維」などにあると考えられています。
食前に摂取された水溶性食物繊維が、後から入ってくる主食(白米)の糖質の吸収を遅らせたり、胃から腸への食物の移動速度(胃排出速度)を遅らせたりすることで、結果として血糖値の上昇が「緩やか」になる、という仕組みのようです。
このメーカーの研究は、「野菜ジュースは血糖値スパイクを起こすから体に悪い」という懸念に対する、強力な反論と言えますね。
ただし、ここには非常に重要な注意点が繰り返されます。この効果は、あくまで「食事の30分前」という特定のプロトコルを守った「野菜ジュース」の研究であり、「野菜生活スムージー」そのものでも、食事と同時でも、単体で飲んだ場合でもない、ということです。
おすすめの飲むタイミングはいつ?
前のセクション(メーカー推奨)で、飲むタイミングが非常に重要だということが分かりました。
「野菜生活スムージー」を飲むなら、その効果を最大限に活かす(あるいはデメリットを最小限にする)ために、いつ飲むのがベストなのでしょうか?
私が調べた情報を元に、目的別のおすすめタイミングを整理してみました。
目的①:食後の血糖値上昇を緩やかにしたい場合(期待)
→ メーカー研究に基づくなら:食事の「30分前」
これは、メーカーの「ベジタブルジュース・ファースト」研究に沿った飲み方ですね。特に、お昼にパスタやラーメン、丼ものなど、炭水化物(糖質)がメインになりがちなランチの30分前に1本飲んでおく、というのが最も効果的なシナリオかもしれません。
「30分前」というのが、職場で実践するにはちょっとハードルが高いかもしれませんが(忘れてしまいそう)、試してみる価値はありそうです。
目的②:間食(おやつ)として
→ おすすめ:活動量の多い「日中」(例:10時や15時)
チョコレートやスナック菓子、あるいは甘い清涼飲料水を飲む代わりに「野菜生活スムージー」を選ぶ、というのは、とても良い選択だと思います。
「遊離糖類」が含まれているとはいえ、ビタミンや製品によっては食物繊維も摂れますし、お菓子よりは健康的かな、と。
ただし、これも「飲みすぎ」は禁物です。1日に何本も飲むと、あっという間に糖類オーバーになってしまいます。飲むなら1日1本(200ml)まで、と決めておくのが賢明ですね。
目的③:栄養補助として
→ おすすめ:野菜が不足しがちな「朝食」のお供に
朝は忙しくて、パンとコーヒーだけ、という方も多いかもしれません。そんな時に、「野菜生活スムージー」を1本プラスするのは、手軽な栄養補助として「ベター・ザン・ナッシング」(何もしないよりはマシ)という観点で非常に有効だと思います。
ただし、この場合(食事と同時)は、血糖値上昇を抑える効果はあまり期待できない、ということは覚えておきましょう。
避けたほうが良いタイミングは?
→ 要注意:活動量が低下する「就寝前」
逆に、あまりおすすめできないのが「寝る前」です。活動量が低下する時間帯に糖類(オリジナルでは13.1gも含まれます)を摂取すると、そのエネルギーが消費されず、体脂肪として蓄積されやすくなる可能性があります。
お風呂上がりにゴクゴク飲みたい!という気持ちも分かりますが、そこはグッとこらえて、水やお茶にしたほうが良いかもしれませんね。
体格や活動量、1日の総摂取カロリーによって影響は異なる点にも留意してください。
市販品を選ぶときのポイント
「野菜生活スムージー」と一口に言っても、オリジナル(紫のパッケージです)や「グリーンスムージー」、「ソイ」(豆乳入り)など、たくさんの種類があります。他社からも様々な製品が発売されていますよね。
「体に悪い」という懸念を少しでも減らすために、市販のスムージーを選ぶとき、初心者の私はどこをチェックすれば良いのか? そのポイントをまとめてみました。
ズバリ、栄養成分表示と原材料名です。
市販スムージー選びのチェックリスト
- 最優先チェック! → 糖類の量まずは栄養成分表示の「糖類」の量を見比べましょう。製品によって、驚くほど差があります。同じシリーズでも、フレーバーによって糖類が倍近く違うことも。できるだけ「糖類」のグラム数が少ないものを選ぶのが、賢明な第一歩です。
- 次にチェック! → 食物繊維の量次に「食物繊維」の量を見ます。前述の通り、搾汁タイプは少なく、添加タイプは多い傾向にあります。「1/2日分の食物繊維」などをうたった製品は、ここが多いですね。自分の目的に合わせて選びましょう。
- 参考チェック → 原材料名の順番「原材料名」は、使用されている量が多い順に書かれています。ここに注目です。
先頭が「野菜」(にんじん、トマトなど)から始まっているか?
それとも「果実」(りんご、ぶどう、バナナなど)から始まっているか?
一般的に、果物が多いほうが糖類も多くなる傾向があります。野菜が先頭に来ている製品のほうが、甘さ控えめである可能性が高いです。(これは絶対ではありませんが) - カロリーも一応チェック糖類と連動しますが、当然カロリーもチェックします。オリジナル(200ml)は67kcal、グリーンスムージー(330ml)は約129kcalなど、製品・容量で差があります。自分の摂取カロリーと相談して選びたいですね。
- 気になる人は → 添加物の有無どうしても添加物が気になる方は、原材料表示を最後までチェックしましょう。「香料不使用」や「無添加」をうたった製品も増えています。
これらのポイントを意識して棚を眺めるだけでも、なんとなく健康そうというイメージ買いを防ぎ、自分に合った製品を選べるようになるかなと思います。
自家製スムージーとの比較
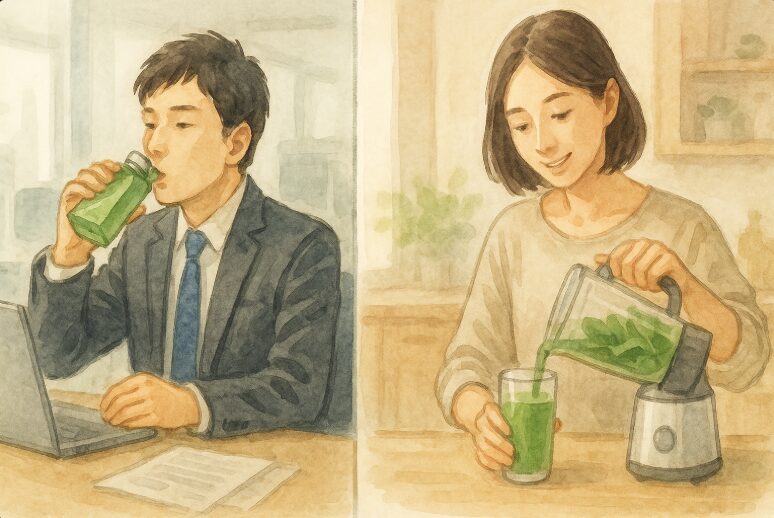
ここまで市販のスムージー(野菜生活など)について深掘りしてきましたが、じゃあ、やっぱり自家製スムージーが最強なの?という疑問が湧いてきますよね。
私も毎朝ミキサーを回している(時々ですが…)人間として、両者のメリット・デメリットを比較してみました。
市販品と自家製、つまりブレンダーやミキサーで丸ごとかくはんするものは、もはや似て非なるものと言っていいほどの違いがあります。
| 属性 | 自家製スムージー(ブレンダー) | 市販のスムージー(野菜生活など) |
|---|---|---|
| 食物繊維(特に不溶性) | ◎ 完全に保持される (皮や種も丸ごと摂取可能。満腹感が非常に高い) | △ 搾汁主体では不溶性が少なめになりやすい(食物繊維を添加する製品では量が多い場合あり) |
| ビタミンC(熱に弱い) | ◎ 加熱による損失はない/作製後は酸化で徐々に減少するため早めに飲むのが望ましい | △ 失われがち (加熱殺菌や保存により損失しやすいため) |
| カロテノイド(熱に強い) | △ 吸収率が低い (生のままでは細胞壁が硬いため) | ◎ 吸収率が高い (加熱処理で細胞壁が破壊され、吸収されやすくなる) |
| 遊離糖類(糖分) | ◎ 調整可能 (ベースを水や豆乳にし、果物の量を減らせば低糖質にできる) | × 高く、固定 (濃縮果汁ベースが多いため、1本10g前後の糖類を含む) |
| 添加物 | ◎ なし (自分で入れたものだけ) | △ あり (品質保持のためのpH調整剤、香料など) |
| 手軽さ・利便性 | × 非常に低い (材料の購入、調理、ミキサーの洗浄が毎回必要) | ◎ 非常に高い (購入してフタを開けるだけ。常温保存も可能) |
結局、どっちを選べばいいの?
この比較表から分かるように、どちらかが絶対的に優れているわけではありません。
【自家製スムージーがおすすめな人】
- 不溶性食物繊維をしっかり摂って、腸内環境や便通を整えたい人。
- 糖質制限中で、自分で糖類の量をコントロールしたい人。
- 添加物を一切摂りたくない人。
- ミキサーの手入れが苦にならない人。
【市販スムージーがおすすめな人】
- とにかく手軽に、野菜不足を補助したい人。(最重要)
- トマトやニンジンのリコピン、β-カロテンを効率よく吸収したい人。
- 食前30分のベジタブル・ファーストを手軽に実践したい人。
- 忙しくてミキサーを洗う時間すらない人。
「体に悪い」という懸念は、主に自家製スムージーの健康効果(高繊維、低糖質、生ビタミン)を市販スムージーに過度に期待してしまった時のギャップから生まれている、というのがハッキリと分かりました。
両者はまったく別の飲み物として、自分のライフスタイルや目的に合わせて使い分けるのが、一番賢い付き合い方ですね。
初心者の自家製レシピ紹介
やっぱり、自家製スムージーも試してみようかなと思った方のために、私がいつも作っている、一番シンプルで初心者向けのグリーンスムージーのレシピを紹介しますね。
自家製のメリットは、なんといっても糖質を自分でコントロールできることです。
基本のグリーンスムージー(低糖質&高繊維)
材料(1人分:約300ml)
- 野菜(葉物): ほうれん草 または 小松菜(生)… 1/4袋(約50g)。クセがなく、スムージー初心者に最適です。
- 甘味(果物): バナナ(冷凍)… 1/2本(約50g)。甘味ととろみが出ます。冷凍バナナを使うと、氷なしで冷たく仕上がります。
- ベース(水分): 無調整豆乳 または アーモンドミルク(無糖)… 150ml。水でもOKですが、豆乳やアーモンドミルクを使うと、タンパク質や脂質が加わり、腹持ちが良くなります。
- (お好みで)脂質: アボカド または ナッツ類… アボカド1/8個、またはアーモンド5粒程度。脂質を加えることで、血糖値の上昇がさらに緩やかになることが期待できます。脂溶性ビタミンの吸収も助けます。
作り方
- ミキサーに、先に水分(豆乳など)と柔らかいもの(バナナ、アボカド)を入れます。
- 次に、葉物野菜(小松菜など)を加えます。
- フタをしっかり閉めて、滑らかになるまで(約30秒~1分)かくはんします。
- 完成です!酸化が進む前に、すぐに飲みましょう。
このレシピのポイントは、甘味をバナナ1/2本に抑えていることです。市販のスムージーは、飲みやすくするために果汁(糖類)がたっぷり入っていますが、自家製ならそれを自分でコントロールできます。
もし甘味が足りなければ、バナナを1本に増やしたり、リンゴやキウイを加えたりしても美味しいですよ。逆に、糖質をさらにカットしたい場合は、バナナを減らして、甘味のないアボカドを増やすと、濃厚でクリーミーなスムージーになります。
ミキサーを洗う手間はかかりますが、野菜を丸ごと摂っているという満足感は、市販品ではなかなか味わえないものがあります。ぜひ一度、試してみてください。
「野菜生活スムージーが体に悪い」の結論
さて、長い時間お付き合いいただき、ありがとうございました。
「野菜生活スムージーは体に悪い」という、ちょっとドキッとするキーワードから始まった今回の調査。最後に、スムージー初心者の運営者として、私なりの最終的な見解をまとめたいと思います。
スムージライフ運営者のまとめ
野菜生活スムージーは、それが毒であるとか、即座に有害であるという意味で体に悪いわけでは全くないと結論付けました。
では、なぜ「体に悪い」と検索されてしまうのか?
その原因は、製品が持つ実態と、私たちが抱く期待やイメージとの間に、大きなギャップがあるからだと思います。
【私たちが抱く期待・イメージ】
「スムージー」という名前から、野菜や果物を丸ごと使った、食物繊維たっぷりで、ビタミン豊富な、低糖質の健康飲料というイメージを期待してしまいます。
【製品の実態】
その実態は、高糖類(遊離糖類)の加工野菜ジュース(搾汁ベース)であり、のどごしのために不溶性食物繊維は相対的に少なくなる傾向があり、ビタミンCも加熱・保存で失われがち。その代わりリコピンの吸収率や利便性を極限まで高めたもの。(※製品によって特性は異なります)
このギャップを知らずに、自家製スムージーの代わりあるいは野菜サラダの完全な代替品として、水やお茶のように1日に何本もゴクゴク飲んでしまう…。
もし、そんな飲み方をしていたら、糖類の過剰摂取などによって、長期的には健康にとって良くない結果(例えば体重増加など)をもたらす可能性が示唆されます。
「体に悪い」という検索は、この飲み方、つまり誤解に対する警告なんじゃないかな、と私は思いました。
免責事項
この記事は、私個人の調査や見解をまとめたものであり、医学的な助言や診断、治療を目的としたものではありません。
健康や食事に関する最終的な判断は、必ず医師や栄養士、管理栄養士などの専門家にご相談ください。特に、糖尿病や血糖値に関する懸念をお持ちの方は、自己判断での摂取は控えてください。

